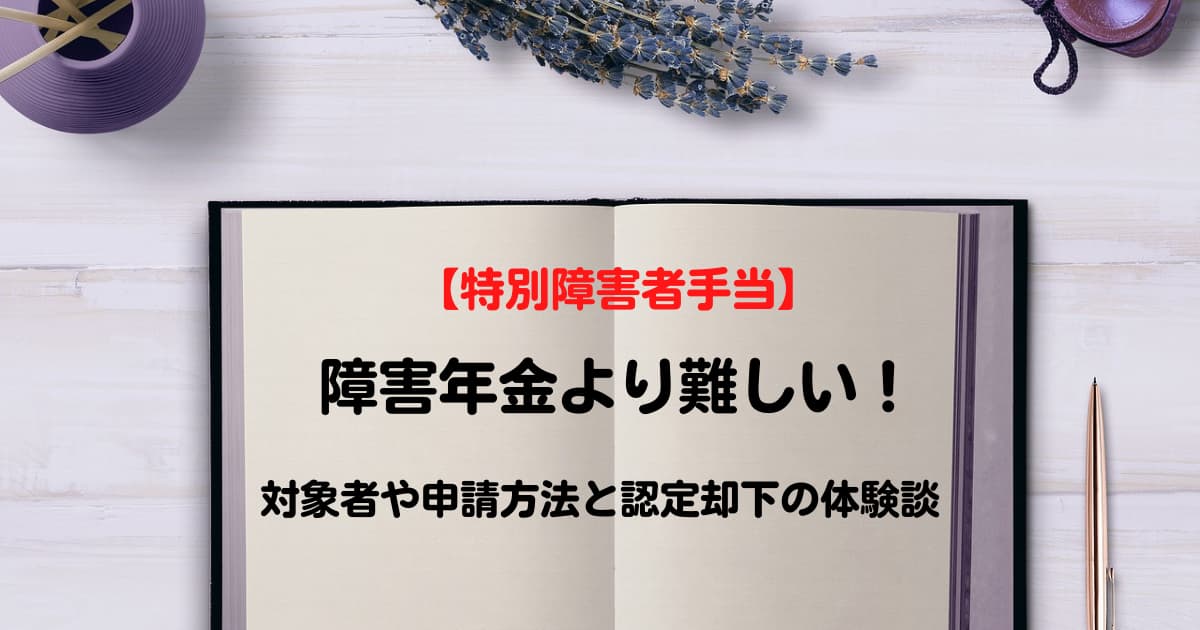「特別障害者手当」って知っていますか?

障害のある子どもが成人したら、どんな助成制度があるのかと漠然とした不安から調べ始めるまでは、私も知りませんでした。
「特別障害者手当」とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅の方に対して支給される手当のことをいいます。
審査がとても厳しく、障害年金が1級でも特別障害者手当の申請を却下されることが多いのが現実です。
この記事では、3歳で発症した小児がんの闘病で晩期障害が残り、7歳で発達障害と診断され、二次障害を発症し引きこもりになった子どもの特別障害者手当の申請した経験から、
- 特別障害者手当とは?
- 特別障害者手当の対象者は?
- 特別障害者手当の申請方法は?
- うちの子の場合の体験談
などについてご紹介します。
「特別障害者手当」とは

「特別障害者手当」とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅の20歳以上の方に対して支給される手当のことをいいます。
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
引用元:厚生労働省

お住まいの自治体によって認定されます。詳しくは、お住まいの市区町村の担当課でご確認ください。
対象となる人
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。
- 20歳未満の方。
- 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されている方。
- 施設などに入所されている方。
所得制限
「特別障害者手当」には所得制限があります。
受給者の所得や、受給者の配偶者および扶養義務者の所得が、所得限度額以上であるときは手当は支給されません。
| 障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 | 当該控除額 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 | |
| 勤労学生控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 | |
| 宴婦控除 | 270,000円 | 小規模企業共済等 掛金控除等 | |
| ひとり親控除 | 350,000円 | ||
| 社会保険料控除 | 80,000円 |
| 扶養親族などの人数 | 受給資格者 限度額 | 配偶者および扶養義務者 限度額 | |
| 所得額 | 所得額 | ||
| 0 1 2 3 4 5 | 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000 | 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 | |
(単位:円、令和3年8月以降適用)
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるとき→1人につき100,000円
- 扶養親族等に、特定扶養親族があるとき→1人につき250,000円
扶養親族等に、70歳以上の老人扶養親族があるとき→1人につき60,000円(扶養親族等が全て70歳以上の場合、1人を除いて加算した額。)

所得額の計算方法は、「所得額=年間収入額-必要経費-諸控除」です。
認定基準
「特別障害者手当」の認定基準は、とても複雑で厳しいものになっています。
単一障害
- ①政令別表第1の8号(内部・その他障害)に該当し、かつ⑥「安静度表」が1である。
- ①政令別表第1の9号(精神障害)に該当し、かつ⑤「日常生活能力判定表」が14点以上である。
- ②政令別表第2の3~5号(肢体不自由)の1つに該当し、かつ④「日常生活動作評価表」が10点以上である。
重複障害
- ②政令別表第2のうち、2つ以上の障害に該当する。
三重障害
①【政令別表第1】
| 第1号 | 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
| 第2号 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
| 第3号 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 第4号 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
| 第5号 | 両下肢の用を全く廃したもの |
| 第6号 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
| 第7号 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
| 第8号 | 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められるものであって、日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの |
| 第9号 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 第10号 | 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
②【政令別表第2】
| 第1号 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
| 第2号 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 第3号 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの、若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 第4号 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 第5号 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 第6号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 第7号 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
③政令第1条第2項第2号】(認定基準表)
| 第1号 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
| 第2号 | 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの |
| 第3号 | 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
| 第4号 | そしゃく機能を失ったもの |
| 第5号 | 音声又は言語機能を失ったもの |
| 第6号 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
| 第7号 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
| 第8号 | 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
| 第9号 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 第10号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 第11号 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
④【日常生活動作評価表】(肢体障害)
| 1 | タオルを絞る(水をきれる程度) | ひとりでできる場合・・・・・・・・・・・・0点 ひとりでできてもうまくいかない場合・・・・1点 ひとりではまったくできない場合・・・・・・2点 (注1)評価表2の動作 ・5秒以内にできる・・・・・・・・・・・・0点 ・10秒以内にできる・・・・・・・・・・・1点 ・10秒以内ではできない・・・・・・・・・2点(注2)評価表3および4の動作 ・30秒以内にできる・・・・・・・・・・・0点 ・1分以内にできる・・・・・・・・・・・・1点 ・1分以内にはできない・・・・・・・・・・2点 |
| 2 | とじひもを結ぶ | |
| 3 | かぶりシャツを着て脱ぐ | |
| 4 | ワイシャツのボタンをとめる | |
| 5 | 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげだしの姿勢を持続する) | |
| 6 | 立ち上がる | |
| 7 | 片足で立つ | |
| 8 | 階段の昇降 |
⑤【日常生活能力判定表】(精神障害)
| 動作および行動の種類 | 0点 | 1点 | 2点 | |
| 1 | 食事 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 2 | 用便(月経)の始末 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 3 | 衣類の着脱 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 4 | 簡単な買い物 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 5 | 家族との会話 | 通じる | 少しは通じる | 通じない |
| 6 | 家族以外との会話 | 通じる | 少しは通じる | 通じない |
| 7 | 刃物・火の危険 | わかる | 少しはわかる | わからない |
| 8 | 都外での危険から身を守る(交通事故) | 守ることができる | 不十分ながら守ることができる | 守ることができない |
⑥【安静度表】(内部障害)
| 1 | 絶対安静 |
| 2 | 終日横になっている |
| 3 | 短時間起床してよいが、主に横になっている |
| 4 | 午前午後にそれぞれ安静時間をとる |
| 5 | 午後安静時間をとる |

認定基準が複雑でわかりにくいですが、簡単にまとめました。
支給額
「特別障害者手当」の手当額は、月額27,350円です。(令和2年4月より適用)

原則として
- 2月(11~1月)
- 5月(2~4月)
- 8月(5~7月)
- 11月(8~10月分)
に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請方法
お住まいの自治体の市区町村の障害福祉課の窓口で申請します。
- 特別障害者手当認定請求書(所定の様式)
- 特別障害者認定診断書 (所定の様式)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(持っている方)
- 年金証書や振込通知書(受給している方)
- 障害のある方の名義の通帳
- 印鑑
- マイナンバー確認書類など
うちの子の場合
うちの子(かっくん)の場合、20歳になって障害基礎年金と同時期に申請しました。
- 3歳「小児がん(肝芽腫)」を発症。
- 化学療法と手術を治療するが入退院を繰り返す。
- 4歳「特別児童扶養手当」(2級認定)
- 再発を繰り返し、自家末梢血幹細胞移植をする。
- 長期の化学療法によりさまざまな晩期合併症が残る。
- 6歳「身体障害者手帳」を取得。(薬剤性感音性難聴、4級)
- 1年生(6歳)「特定できない広汎性発達障害」と診断受ける。
- 2年生(7歳)「療育手帳」を取得。(判定B-2)
- 5年生(11歳)「特別児童扶養手当」(1級認定)
- 5年生(11歳)「障害児福祉手当」申請→認定。
- 15歳「精神保健福祉手帳」を取得。(2級)
- 20歳「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」資格喪失。
- 20歳「障害基礎年金」(1級認定)
- 20歳「精神保健福祉手帳」を取得*。(1級)
*(障害年金受給(1級)の決定により、年金証書での等級変更申請。)

障害年金の手続きに力を入れていて、特別障害者手当の認定基準については、あまりよく理解していませんでした。
| 1回目 | 「精神障害」での診断書で申請。 (障害児福祉手当の診断書と同じ) | 単一障害では、①の9号の精神障害に該当するが、⑤日常生活能力判定が14点以下のため、認定却下。 |
| 2回目 | 「その他の障害」の診断書追加。 | 重複障害では、②の7号の精神障害は該当するが、②の他の障害の基準に該当しないため、認定却下。 |
| 3回目 | 「聴覚障害」の診断書追加。 | 重複障害では、②の7号の精神障害には該当するが、②の他の障害の基準に該当しないため、認定却下。(聴覚障害では、言語明瞭度*の判定はしない。) |
*言語明瞭度とは、耳から入ってきた音を言葉に変換する力が弱く、いくら音を大きくしても言葉としてはっきりと聞こえないことをいいます。

うちの子(かっくん)は、小児がんの治療の晩期障害として障害が残りました。
聴覚障害では、言語明瞭度が40%未満で、言葉として聞き取ることが難しくサポートが必要です。曖昧な認定基準が多く、どのような状態なのかを質問していたところ、「誰とも会話ができない状態である」との回答をもらいました。
》【障害年金】対象者や等級、認定基準や請求手続きなどをわかりやすく解説します!
》【障害年金】精神疾患のある場合の対象者や障害等級などをわかりやすく解説します!
》【障害年金】20歳前傷病による障害基礎年金の病歴・就労状況申立書の書き方【体験談】
まとめ
「特別障害者手当」とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅の20歳以上の方に対して支給される手当のことをいいます。
認定基準が複雑でわかりにいことや審査がとても厳しく、障害年金が1級の認定を受けていても、特別障害者手当の認定を却下されることが多いのが現実です。
将来のことを考えて、少しでも自分でできることを増やすために、親も子どもも、嫌な思いやトラブルなどがありながらも一生懸命に悪戦苦闘してようやくできることが増えると、成人してからの経済的なサポートが受けられなくなるというのが、現在の福祉制度のようです。
重度の障害のある子どもが、成人して在宅で生活していくには、常にサポートが必要となります。
さまざまな理由で他人と関われることができないこともあり、それを支える家族にとっては、経済的な負担が大きいこともまた現実です。
周囲の理解が得られないことや適切な対応を望めないことなども多く、精神的な不安や経済的な不安から、精神的に追い詰められてしまうこともあります。
うちの子の場合は認定されませんでしたが、認定されれば経済的な大きな支えとなり、少しでも負担を減らすことにもなりますので、該当される方は申請してみてはいかがでしょうか。