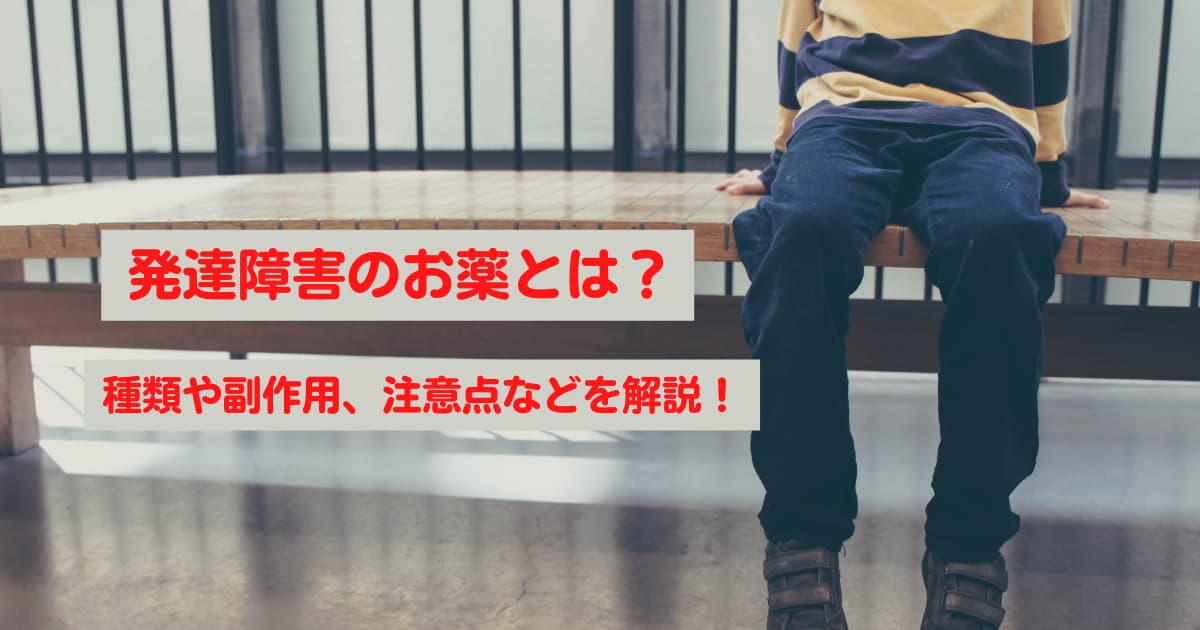発達障害と診断されて、お子さんにお薬を飲ませていいのか、飲ませない方がいいのか悩まれている保護者の方も多いのではないでしょうか。風邪や発熱とは違い、発達障害の特性は「薬を飲んだから」といって治るものではありません。

基本的には、発達障害の特性への理解や関わり方や、特性による環境作りなどが一番大切になります。
発達障害で使用される「薬物治療」は、発達障害の特性の困難さ、生きにくさからの精神的な症状や行動的な問題などが、日常生活に支障をきたす症状に合わせて処方されます。
この記事では、3歳で発症した小児がんの闘病や、7歳で「発達障害」と診断を受け、二次障害を発症し引きこもりになった子どもとの波乱万丈な経験から、
- 発達障害のお薬とは?
- くすりの種類や副作用は?
- 注意点はある?
- うちの子の場合の体験談
などについてご紹介します。
発達障害のお薬とは
発達障害の子どもへの対応は環境整理が第一です。薬物を使用するのはそれにもかかわらず家庭や学校・園で著しい適応障害がある、自己や他者に身体的危険が及ぶ可能性が高い時などです。 自閉症スペクトラムの子どもでは、環境理解の悪さ、因果関係の理解困難などから、物事の見通しが立たず常に不安な状態にあることが多く、イライラ感やパニックを引き起こします。また、状況判断の間違い、コミュニケーションの障害から被害感を生じ、乱暴な行動、攻撃行動、多動性・衝動性や不注意が見られることもまれではありません。この攻撃行動が内に向かえば自傷行為となります。乱暴な行動の背景にいじめやからかいが潜んでいる可能性にも注意を払うべきです。「こだわり行動」は生活に支障のないものは放置してもかまわないですが、「こだわり」のため家庭や学校・園での生活の流れに支障をきたす場合には治療の対象となります。
引用元:発達障害の子どもにはどういう薬が用いられるのでしょうか?|日本小児神経学会
- 「療育」
- 「生活環境の調整」
- てんかん発作
- 睡眠障害
- 多動性、衝動性、攻撃性、不注意、興奮、自傷行為など
- 二次的な精神症状(不安、うつ、緊張、興奮しやすさなど)
- 問題行動(暴言・暴力、自傷行為など)

発達障害の「薬物治療」は、少ない用量から始めます。副作用が出ていないか確認しながら、効果がみられる最小量を使って慎重に様子を見ていきます。
お薬の種類

中枢神経刺激薬
メチルフェニデート徐放剤
ナルコレプシーやADHDの治療に用いられる精神刺激薬。
| 効能 | 副作用 | |
| リタリン | 脳神経の活動を活発にして眠気を除去する。 | 頭痛 / 不眠 /眠気 /口渇 / 食欲不振 など |
| コンサータ | 脳内の神経細胞の間で情報を伝える神経伝達物質(ドパミン、ノルアドレナリン)を増加させ、神経機能を活性化し、注意力を高めたり、衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善する。 | 食欲減退/不眠症/体重減少/頭痛/腹痛など |
強い不安・緊張、うつ病、チックなどを持つ場合は禁忌とされています。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなくてはなりません。自己判断で服薬を中止せず、必ず医師に相談するようにしましょう。
アトモキセチン塩酸塩
脳内の神経伝達機能を改善し、注意力の散漫や衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善する薬。
| 効能 | 副作用 | |
| ストラテラ | 前頭前野におけるノルアドレナリンとドーパミン濃度を上昇させることで注意・実行機能を活性化する。側座核やチックに関与する線条体のドーパミン濃度を上昇させないため、薬物乱用は生じない。 | 頭痛/消化器症状/傾眠など |
抗精神病薬
さまざまな脳内神経伝達物質のうちの、主にドパミンのD2受容体を遮断することにより、精神病症状を緩和します。
定型抗精神病薬
ドパミンのみを抑制する作用があり、第一世代の抗精神病薬。
| 効能 | 副作用 | |
| ハロペリドール | 中枢神経に作用し強い不安感、興奮を改善し、幻覚・妄想を抑え、精神状態を安定させる。 | 手足のふるえ/筋肉のこわばり/不眠/全身倦怠感/食欲不振など |
| クロルプロマジン | 脳内の情報伝達系の混乱を改善し、主にドーパミンという神経伝達物質を抑える。 | 手のふるえ/体のこわばり/つっぱり/口の渇き/立ちくらみ/動悸など |
非定型抗精神病薬
ドパミンだけでなくセロトニンやその他の神経伝達物質への作用がある、第二世代の抗精神病薬。
| 効能 | 副作用 | |
| リスペリドン (リスパダール) | 脳内の情報伝達系の混乱を改善し、主にドーパミンとセロトニンという2つの神経伝達物質を抑え、統合失調症の陽性症状(幻覚、妄想、興奮)と陰性症状(無感情、意欲低下、自閉)の両方によい効果を発揮する。 | 立ちくらみ/めまい/眠気/口の渇き/便秘/尿が出にくい/動悸/体重増加など |
| オランザピン (ジプレキサ) | 眠気/立ちくらみ/めまい/口の渇き/便秘/動悸/体重増加など | |
| アリピプラゾール(エビリファイ) | 体の勝手な動き/じっとできない/手足のふるえ/不眠/眠気/体重増加など |
一部の薬剤では、糖尿病の方には使用できない等の注意が必要です。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなければなりません。
抗うつ薬SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
脳内の神経伝達を改善し、意欲を高めたり、憂鬱な気分などを改善する薬。
| 効能 | 副作用 | |
| セルトラリン (ジェイゾロフト) | セロトニンは、気分にかかわる神経伝達物質のこと。セロトニンを再取り込みするセロトニントランスポーターの働きを阻害することで、脳内シナプス間隙のセロトニン濃度が高まり、神経の伝達がよくなる。 | 吐き気/嘔吐/下痢/便秘眠気/めまい/頭痛など |
| フルボキサミン(デプロメール) (ルボックス) | ||
| パロキセチン (パキシル) | ||
| エスシタロプラム(レクサプロ) |
眠気、めまい、頭痛などの精神神経系症状が現れることがあるため、自動車運転などは十分な注意が必要です。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなければなりません。
抗不安薬(ベンゾジアセピン系)
脳の興奮などを抑えることで不安、緊張、不眠などを改善する薬。
| 効能 | 副作用 | |
| ジアゼパム | 脳のリラックス系の神経受容体「BZD受容体」に結合することで、リラックス系の神経を活性化させる。抗不安作用、鎮静・催眠作用、筋緊張緩和作用、抗けいれん作用をあわせ持つ。 | 眠気/ふらつき/倦怠感/脱力感など |
| クロキサゾラム(セパゾン) | ||
ロラゼパム (ワイパックス) |
脳内の活動をスローダウンさせるため、車の運転や危険な作業は控えたほうがよいでしょう。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなければなりません。
抗てんかん薬
脳内神経の過剰な興奮を抑えることで、てんかん、躁状態などを改善する薬。
| 効能 | 副作用 | |
| カルバマゼピン (デクレトール) | 脳の神経を鎮めて、気分の高ぶりをおさえ落ち着かせ、躁病や躁うつ病のほか、さまざまな精神疾患による不安や緊張、興奮状態を鎮める。 | 眠気/めまい/けん怠感/頭痛/吐き気/口の渇きなど |
| バルプロ酸 (デパケン) | 脳神経の興奮をおさえて、てんかん発作を予防し、怒りやすい、不機嫌という てんかんにともなう性格行動障害を改善する。 | 眠気/ふらつき/吐き気/食欲不振/倦怠感など |
| クロナゼパム (リボトリール)(ランドセン) | 脳の神経を鎮めて、てんかん発作が起こりにくい状態にする。 | 眠気/ふらつき/脱力感など |
脳の神経細胞の過剰な興奮を抑制する作用が過剰になった場合、中枢神経が抑制され、眠気やふらつきなどの症状があらわれます。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなければなりません。
抗ヒスタミン薬
神経伝達物質ヒスタミンの働きを抑えることでアレルギー反応の蕁麻疹、花粉症、喘息などの皮膚の腫れや痒み、鼻炎(くしゃみや鼻みずなど)、咳などの症状を改善する薬。
| 効能 | 副作用 | |
| ヒドロキシジン (アタラックス) | アレルギー症状を抑える作用と、気分をリラックスさせる作用をあわせ持つ。 | 眠くなる/だるさなど |
車の運転や危険な作業は控えたほうがよいでしょう。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなければなりません。
グアンファシン塩酸塩
脳内の神経伝達機能を改善し、注意力の散漫や衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善する薬。
| 効能 | 副作用 | |
| グアンファシン (インチュニブ) | ノルアドレナリンの神経受容体であるα2A受容体を選択的に刺激することで神経伝達を増強させる。 | ひどい眠気/低血圧/徐脈など |
心臓病のある人は、病状の悪化に注意が必要です。血圧が低めの人は、さらになる低下に注意が必要です。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなくてはなりません。
リスデキサンフェタミン メシル酸塩
脳内の神経伝達機能を改善し、注意力の散漫や衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善する薬。
| 効能 | 副作用 | |
| リスデキサンフェタミンメシル (ビバンセ) | 神経伝達物質のドパミンやノルアドレナリンの活性化が、さまざまな症状を改善させる。 | 食欲不振/吐き気/不眠/頭痛など |
不眠症状があらわれる場合もあるため、午後の服用は避けます。また、飲み合わせに注意が必要なこともあるので、必ず専門の医師の診断のもとで慎重に使用しなくてはなりません。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療薬
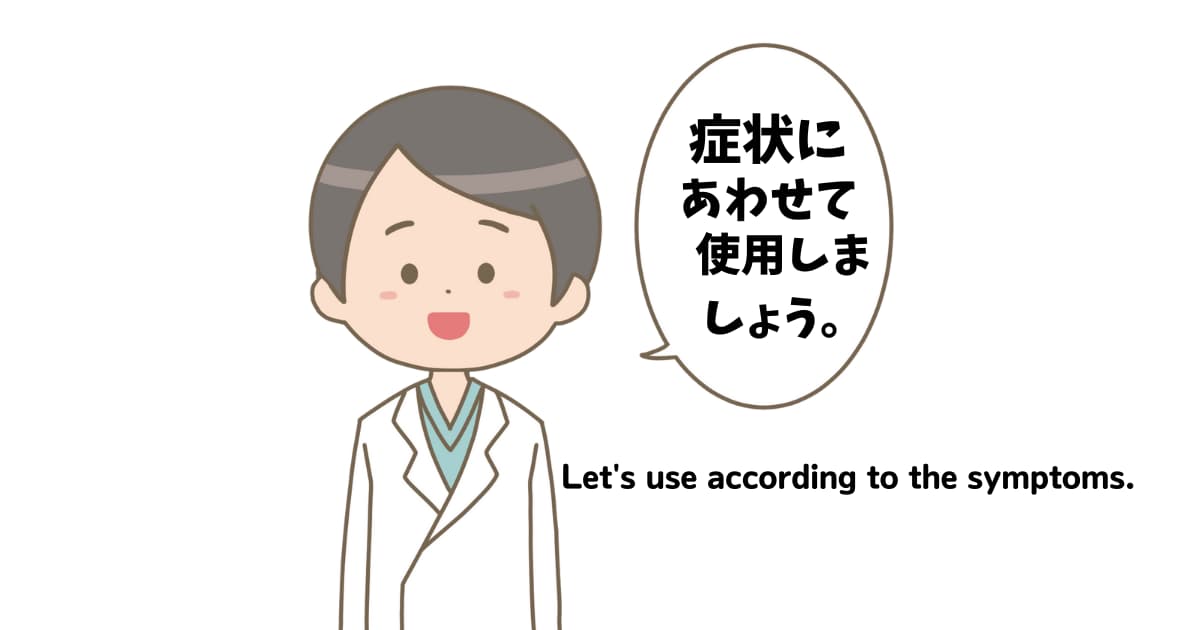
日本で、注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療薬として使用されます。
①コンサータ(メチルフェニデート製剤)
- 主に脳内のドパミンとノルアドレナリンの働きを強める作用。
- 1日1回の服用で、約12時間効果が持続。
- 速効性と持続性をあわせ持つのが特徴。
- 副作用で、寝つきが悪くなることなどがあるため、原則は午後の服用は避ける。
②ストラテラ(アトモキセチン製剤)
- 主に脳内のノルアドレナリンの働きを強める作用。
- 脳の覚醒が比較的少なく、ADHDの治療ができる。
- 服用開始2週間くらいから少しずつ効き始め、6~8週目で効果が安定。
③インチュニブ(グアンファシン製剤)
- 主に脳内のノルアドレナリンの受容体であるα2A受容体を刺激し、シグナル伝達を改善する作用。
- 薬理作用から「選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬」に分類。
- 効果発現は、服薬開始後1~2週ぐらい。
④ビバンセ(リスデキサンフェタミン製剤)
- ノルアドレナリンとドパミンのトランスポーター阻害作用や、ノルアドレナリンとドパミンの遊離作用などにより、シグナル伝達を改善。
- d-アンフェタミンの急激な血中濃度上昇が抑制されるため、血中濃度の維持とともに、効果の持続性が期待。
- 不眠症状があらわれる場合もあるため、午後の服用は避ける。
- この薬は発売後間もないため、使用経験が蓄積されるまでの間は、他の治療薬が効果不十分な場合に限り使用。

お薬についての用法用量は、医師・薬剤師の指示を必ずお守りください。心配なことがあれば、医師に相談しましょう。
うちの子の場合

うちの子の場合は、発達障害の診断と同時にお薬を始めました。二次障害が起きてからは、症状も複雑になってくるので、お薬の種類も少しづつ変わっていきました。
| ①オーラップ | 攻撃性や暴力を抑えるため処方。 | 変更。 |
| ②デクレトール | てんかん発作があり、脳波異常があるため処方。 | 血小板減少症の副作用により中止。 |
| ③リスパダール | 攻撃性やパニックが頻繁にあり処方。 | 変更。 |
| ④デプロメール | ③リスパダールに追加で処方。 | 変更。 |
| ⑤エビリファイ | 感情のコントロールができず、パニックが続くため処方。 | 変更。 |
| ⑥ロゼレム | 不眠が続くため⑤に追加して処方。 | 効果がないので中止。 |
| ⑦ジェイゾロフト | セロトニン濃度を高め、神経の伝達がよくなるよう処方。 | 継続。 |

うちの子の場合は、小児がんでの晩期障害での身体の障害などがあるため、そのための内服もしています。薬の処方には慎重に医師と相談し、少しでもおかしいと感じたときには変更したり増減したりを心がけています。
下記で、発達障害の二次障害について紹介していますので、参考までにどうぞ。
》【発達障害】二次障害にはどんな症状がある?発症すると治りにくい【うちの子の場合の体験談】
まとめ
発達障害のお薬は、さまざまな種類が種類があり、それぞれの症状に合わせて使用することが大切です。基本的に発達障害の対応は、発達障害の特性への理解や関わり方や、特性による環境作りなどが一番大切になります。
あらわれている症状が生活において支障をきたす場合には、薬物治療も必要です。うまく適応出来なくて自分を責めるようになり、うつ症状が出る場合もありますし、パニックが頻繁に起きることで、精神的に不安定になり、強迫性障害や不安障害などにつながる場合もあります。
副作用が起こることもあるため、主治医とよく相談しながら、納得した上で指示どおりに服薬しましょう。
自己肯定感アップ!我が子に合った「ほめ方」がわかる! 伝え方コミュニケーション検定
リンク