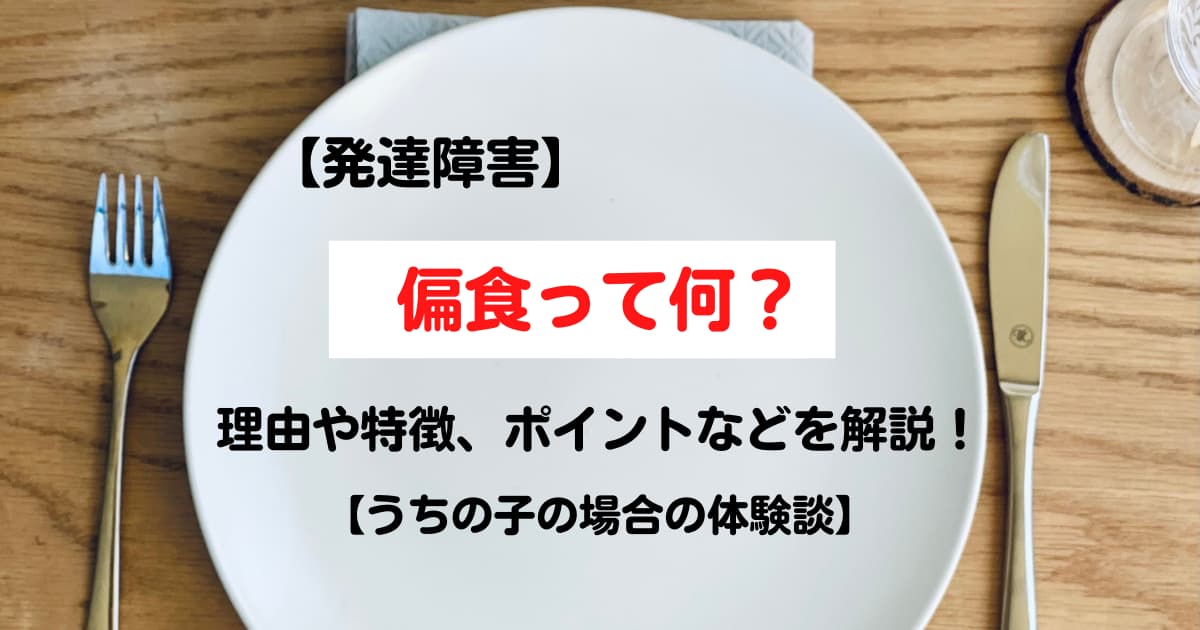「偏食」って知っていますか?食事の好き嫌いって誰でもあるし、子どもの頃は食べず嫌いや野菜が苦手なお子さんは多いものです。

どうにか食べさせようと、細かくしたり、すりおろしたり形を変えたりなど努力されている方も多いのではないでしょうか。
「偏食」とは、「特定のものしか食べない」や「見覚えのないものは絶対口に入れない」など、「食べれるもの・食べれないもの」がはっきりしていることをいいます。
発達障害のある子どもの多くは「偏食」に悩まされることも多く、実際に私の子どもも極度の「偏食」があり、長年の悩みでもあります。
この記事では、3歳で発症した小児がんの闘病や、7歳で発達障害と診断を受け、二次障害を発症し引きこもりになった子どもとの波乱万丈な経験から、
- 偏食とは?
- 発達障害と偏食は?
- 偏食の理由は?
- うちの子どもの場合の体験談
などについてご紹介します。
偏食とは
偏食とは、必要な栄養素に偏りがある食事をすることをいいます。

好き嫌いと違うの?
神奈川県立こども医療センター(横浜市)の田上幸治医師によると、ASDの特徴の一つに味覚や嗅覚、視覚などの感覚過敏がある。酸味や辛み、苦みなどを異常に強く感じたり、食感や温度にこだわりを持ったりして受け付けないことがある。さらに、田上医師は「コミュニケーションが苦手なことも偏食の克服を難しくする。食べられる食品が15品以下の場合は、ビタミンやミネラルが極端に不足するなど栄養障害になりやすい」と話す。
引用元:西日本新聞
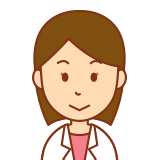
発達障害がある方には、感覚過敏の特徴がある場合が多く、その特徴によって偏食になる傾向があります。
発達障害とは
| 自閉症スペクトラム症 | 対人関係が苦手で、強いこだわりがあるという特徴をもつ発達障害の1つ。 |
| アスペルガー症候群 | 社会性やコミュニケーション、こだわりの強さや感覚過敏などの特徴がある発達障害の1つで、知能や言語の遅れがないもの。 |
| 注意欠陥多動性障害(AD/HD) | 「不注意」「多動」「衝動性」などの特徴がある発達障害の1つ。 |
| 学習障害(LD) | 全般的な知的発達に遅れはないが、特定の能力を学んだり行ったりすることなどに困難が起こる特徴がある発達障害の1つ。 |
| トゥレット症候群 | 音声チックをともなう複数の運動チックなどが、 1年以上続く精神神経疾患のこと。 |
| 吃音症 | 言葉がスムーズに話せないなど、話を始めるときに最初の言葉に詰まったり、同じ音を繰り返したりする言語障害の1つ。 |
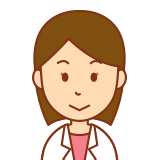
発達障害の特徴は1人ひとり違いますが、
- こだわりがある
- パターン化した行動
- 興味や関心の偏り
が強く、食事についても特徴があらわれる場合があります。
発達障害と偏食
発達障害の特徴によって、極度の偏食になる場合があります。
- 同じものしか食べない。
- 食感が気持ち悪い。
- 食べたことのないものを口にするのが怖い。
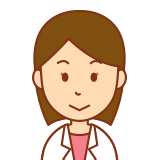
感覚過敏の1つでもある味覚過敏により、食感が極度に過敏であり、
- とろみのあるもの
- グチャグチャしたもの
- パサパサしたもの
などの食感がダメだということもあります。
感覚過敏がある
感覚過敏とは、五感から受け取る刺激を、過剰に強く感じる状態のことをいいます。
| 聴覚過敏 | 生活の電子音、冷蔵庫やエアコンの音、人の声や周囲の雑音が騒がしく聞こえる。 |
| 視覚過敏 | 太陽光やパソコンの画面、真っ白い紙などが眩しく感じる。 |
| 触覚過敏 | 衣服によっては肌にあたる感触で着れなかったり、ヌルヌルしたものを触れない、他人との握手が苦手。 |
| 嗅覚過敏 | 犬並みの嗅覚を持ち、生活用品から外の匂い、大気の匂いなどのにおいに敏感で、吐き気や頭痛につながる。 |
| 味覚過敏 | 独特な食感や、舌ざわりの食べ物が苦手なため、極度の偏食につながる。 |
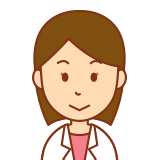
味覚だけでなく、さまざまな環境の影響を受けやすい場合もあります。

環境によっては、どんなにお腹がすいていても食べないどころか、癇癪を起こしたりと問題行動に繋がることもあるんですよね。
こだわりが強い
こだわりが強いとは、自分の好きなものにはとことんこだわるということです。
- コンビニの○○味のおにぎりしか食べない。
- お菓子は○○のメーカーの○○しか食べない。
- 味が混ざるのが嫌。
- 白いご飯が食べれない。
- お肉の脂身が嫌。
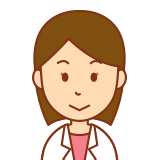
このこだわりは、本人の心地よさに関係しているため、一般的な好き嫌いと誤解されやすく、「わがままだ」と叱責されやすいです。

理解できない原因なことが多いので、親の育て方のせいなのではと悩むんですよね。
マイブームがある
マイブームとは、今現在の興味や関心があるものやお気に入りなもののことをいいます。
- 同じものを毎日食べる。(カレーブーム、ふりかけブーム、コンビニおにぎりブームなど。)
- 同じお菓子を毎日食べる。(ポテトチップス○○味ブームなど。)
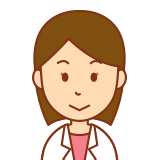
食べ方にも自分なりのルールがあり、それが1つでも崩れるとパニックを起こす場合があります。

例えば、同じ味でもポテトチップスのメーカーが違うと絶対に食べません。
嫌な記憶のフラッシュバック
学校の給食の時間などで、嫌な出来事があった場合はその記憶が同じような場面でフラッシュバックしてしまうことがあります。
- 食べれないのに、一口食べて気持ちが悪くなった。
- 嫌いなものを無理に食べて、その後吐いてしまった。
- 残した食器を片付ける際に、手について気持ち悪くなった。
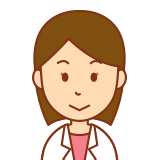
学校での給食は、偏食のある子どもにとっては地獄の時間にもなります。「一口でいいから」と無理やり食べさせることは、嫌な記憶がトラウマとして残ってしまう場合があります。

食事と嫌な記憶が結びつくと、その後の生活に大きく影響してしまうので、食べれる物が増えた時に喜ぶなど、気持ちに寄りそうことが大切ですね。
偏食も受け入れよう
子どもの偏食は、どうしたらいいのかと親にとっては大きな悩みですよね。
無理強いはしない
だまし討ちをする事は、絶対に止めましょう。
- 細かくする。
- すりおろす。
- つぶす。

感覚過敏があるとほんのわずかな変化などに気付くので、トラブルの原因になります。その後の信頼関係に影響するほどの問題にもなりかねないので、注意が必要です。

入ってないと嘘をついて、ボクをだますんだ!もう信じられない!

こうなってしまうと、癇癪や暴言が酷くなり、気持ちを落ち着かせるのにとても時間がかかります…。
食べれるものを食べよう
食べれるものを食べることが大切です。
- 食事の時間を楽しむ。
- 本人が美味しいと思うことを受けいれる。

偏食には、理由があって食べれないことがほとんどです。その理由を受けいれることで、食事の時間が楽しい時間だと思えることが大切です。
自分から食べてみたいといった時がチャンス
年齢と共に、味覚も少しづつ変わってきます。
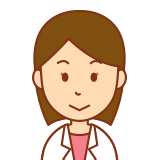
一般的にも、「子どもの頃は食べれなかったけど、大人になったら美味しく食べられた」ということがあります。
- 年齢や体調などと共に、味覚が変わってくる。
- 少しづつ食べてみたいものが増えてくる。
- 新商品などの情報がたくさん入る。

「○○を食べてみたい。」と言った時がチャンスです。料理したり、買ってきたり、次の食事の時に準備して、まず挑戦してみることです。食べれなかった場合も、怒ったりせず受け入れることが大切です。
【体験談】うちの子の場合
うちの子(かっくん)の場合は、極度の偏食です。

3歳になるまでは、苦手な野菜はあるけれどそれなりに何でも食べれていました。保育園に行っていたので、給食も食べていましたよ。
小児がん発症
3歳で小児がん(肝芽腫)を発症し、闘病生活を送りました。肝芽腫とは、子どもの肝臓にできるがんのことです。
- 肝臓全体に散らばっているステージⅣ。
- 化学療法、切除手術、自己末梢血幹細胞移植を行う。
- 抗がん剤の治療が始まると、副作用で食べれなくなる。
- 抗がん剤が体に入ることで、気持ち悪くなり嘔吐する。
- 食べれない時は、高カロリー輸液を使用する。

治療が始まると、食べれないことが続きます。病院食は、子どもには好まないものばかりで、好きなものや食べれるものを食べるようにしていました。
- アイスやチョコムース
- スナック菓子
- そうめん
- 鮭弁当の鮭
6歳になる頃に寛解となりましたが、長期の抗がん剤治療の後遺症(晩期合併症)が残りました。

3歳から突然始まった入院生活で、かっくんの食事は大きく変わりました。食べたいけど食べれないという状況が長く続いたことは、その後の食生活にも大きく影響がありました。
- 3歳から始まった入院生活と闘病生活で食生活が変わる。
- 食べたいけど食べれないを繰り返す。(食べても吐いてしまう)
- 状態によって生食禁止などがある。
下記で、小児がん(肝芽腫)についての体験談などを紹介していますので、参考までにどうぞ。
》【小児がん】肝芽腫って何?症状や診断、治療法などをわかりやすく解説【体験談】
》【小児がん】晩期合併症って何?障害の種類や症状などをわかりやすく解説【体験談】
退院後のご飯

退院後、家に戻ってきてからは、今まで食べれなかった分、好きなものを食べることを意識して料理しましたが、味覚や感触が変わってしまい食べれるものが減っていました。
- 子どもが好きなものを何種類も作った。
- お弁当にしたり、一口サイズにしたり、形や環境を変えてみる。
入院する前は食べれていたものでも食べれなくなっていて、食感に敏感になっていました。

自己末梢血幹細胞移植の際の前処置の大量化学療法では、抗がん剤を大量に投与するため、副作用で口の中がただれます。水を飲むのも難しく、口から火が出ているような痛みで、氷をくるんだガーゼで冷やすことしかできない状態になります。それから口に入れるものに慎重になり、食感が少しでも不快だと吐き出すようになりました。
発達障害の診断
小学部に入学したころからトラブルが増え始め、7歳で「特定できない広汎性発達障害」と診断されます。
- 集団行動になじめない。
- 教師や友達とのトラブルが絶えない。
- 家でも伝わらないことが多い。
- 癇癪がひどく暴れることが多い。
- 薬物治療を開始。
下記で、発達障害と診断されるまでについて紹介していますので、参考までにどうぞ。
》【発達障害】うちの子、何かが違う?と感じた気づきの特徴やポイントを解説【体験談】
》【発達障害】薬物療法のくすりの種類や副作用、注意点などを解説【体験談】
給食の時間

食べるものが少ないので給食は心配でしたが、無理やり食べさせることはなく、食べれるものを食べるように学校とも話し合っていました。
- 給食以外での教師や友達とのトラブルが増える。
- 叱責されることが多く、イライラしている。
- 自分は悪い子だと自信をなくす。

気持ちが不安定になると、感覚過敏が鋭くなり、これまでに食べれていたものも食べれなくなるなど食事にも影響するようになります。
二次障害と不登校
二次障害を発症し、学校への行きしぶりが始まると、給食の時間が問題になります。
- 短時間でも登校する時は、給食の時間を避ける。

気持ちが不安定な状態が続くとこだわりが強くなり、家でも食事のレパートリーが徐々に少なくなっていきました。ルーティーンやマイブームに強くこだわるようになります。
下記で、発達障害のある子どもの二次障害について紹介していますので、参考までにどうぞ。
》【発達障害】二次障害にはどんな症状がある?発症すると治りにくい【うちの子の場合の体験談】
年齢と共に変わる味覚
「子どもの時に食べれなかったものが、大人になったら食べれるようになる」ことはよくある話です。
- カレー、シチュー、ハヤシライスなどの具材を除いたルーのみを、ご飯にかけチーズを乗せ、ドリア風にしたもの。
- ベーコンや皮なしウインナーなど。
- 白いご飯では食べない。
- セブンイレブンの鮭おにぎり(海苔はなし)

年齢が上がるとともに、味覚が少しずつ変わったのか、ルーティーンやこだわりの内容が変わっていきました。
- ココイチのレトルトカレー(ナチュラルチーズを入れる)
- セブンイレブンのツナマヨおにぎり
- 青の洞窟シリーズのカルボナーラ
- 魚介類の具材を抜いたカップヌードル
- 鮭フレークで作る鮭ボールおにぎり
- 豚肉の薄切り肉での焼肉と白ご飯
- 堅あげポテトののりしお

白ご飯は、焼肉、キョウザ、サバの味噌煮とは一緒に食べれるようになりました。野菜は、どうしても無理ですが、たま~に気が向いたら野菜ジュースを飲みます。
セブンイレブンのツナマヨ一択の子どもが美味しいといったレシピをご紹介します。
https://cookpad.com/recipe/1269138

現在25歳になりましたが味覚が大幅に変わり、ちょっとずつ自分の体を気にするようになり食べる物も意識するようになりました。
- 食べれなかった野菜→キャベツの千切り(シーザードレッシングかけ)
- ご飯、豆腐の味噌汁、だし巻き卵、さばの塩焼きの定食セット
- そのままのカップヌードル(具材を抜かなくても食べれる)
- 甘いジュースが苦手になる
まとめ
「偏食」とは、「特定のものしか食べない」や「見覚えのないものは絶対口に入れない」など、「食べれるもの・食べれないもの」がはっきりしていることです。
発達障害があると感覚過敏の特徴がある場合が多く、その特徴によって偏食になる傾向があります。
- 感覚過敏がある。
- こだわりが強い。
- マイブームがある。
- 過去の嫌な記憶がある。
偏食の理由や原因は1人ひとり違いますので、それぞれに合わせた対応をすることが大切です。
- 無理強いはしない。
- 食べれるものを食べる。
- 食べてみたいという時がチャンス。
病気やアレルギーなどで、食べたくても食べれないこともあります。偏食だとしても、美味しいと思えるものを食べるということは人間が生きていくうえでとても大切なことです。
食べれないことを一番気にしているのは本人なので、食べることが嫌いにならないように気持ちに寄りそうことがとても大事です。